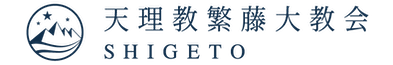読んで良かったら「スキ」押してね ♪

シリーズ
「かしもの・かりものの理」を深く掘る vol.9
前号をまだ未読の方は、よければこちらもご一読いただきたい。
- 早い信仰と遅い信仰(2025.3)
- 急ぐ必要はない、あえて遅らせよう(2025.4)
- 神の身体と天然自然(2025.5)
- 「令和の米騒動」と天理教(2025.6)
- 選挙と天の理(2025.7)
- 子供に伝える、神様のおはなし(2025.8)
- 子供に伝える、”ひのきしん” のおはなし(2025.9)
- 夫婦問題と天の理(繁藤月報-巻頭言 2025.10)
§ § § § § § § § § § §
「エンディングノートなんか本当は書かなくてもいいんですよ」
4000件以上の相続に携わってきた「相続のプロ」がぽつりとつぶやいたその言葉に、私は驚いた。
エンディングノートを書けば安心?
先日、繁藤大教会主催で「終活・相続勉強会」を開催した。前半、相続に関する講座は相続のプロに頼み、後半は終活について私がそのコマを担った。
まずエンディングノートとは、これまでの人生を振り返りつつ、万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことなどを書き留めるものだ。具体的な項目をあげれば、終末医療や葬儀、財産などについての希望を記す。
実際に自分もエンディングノートとにらめっこしてみてまず感じたのは、これは老若男女すべての方におすすめしたいということだ。いつ死が訪れるかわからないだけに、準備をするにこしたことはない。
一方で、エンディングノートを書いてみて、私の心に生まれたのは安心感ではなかった。それどころか「死にたくない」という気持ちが強くなったのだ。また自分だけでなく、仮に親がエンディングノートをちゃんと書いているからといって、いつ親を見送ってもいい。そんな気持ちにはとてもなれそうになかった。
死ぬのは嫌だ。身近な人が死ぬなんて考えたくもない。そう思うのは、別に私に限ったことではないだろう。そもそも、昔からこの「死」という問題に向き合うのが宗教の大きな役割だ。エンディングノートを書いたくらいで、そう簡単に割り切れるものではない。
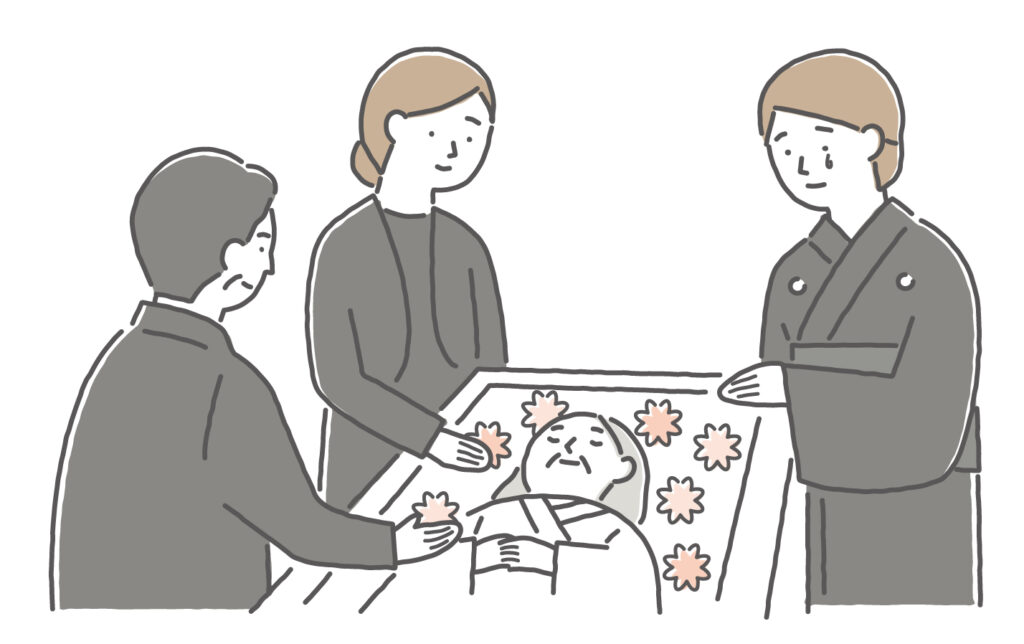
考えてもらいたい3つの質問
誰しも死ぬのは怖いし、嫌だ。紀元前、中華統一をした秦の始皇帝はすべてのものを手に入れた。たった一つ、手にすることが叶わなかったのが不老不死である。始皇帝は永遠の命を求め、水銀を不老不死の妙薬と信じ、死を迎えた。
医療技術が進んだ現代でも、本質的に老いには抗えない。
そこで皆さんに一つ目の質問だ。
「あなたは何歳まで生きたいですか?」今、人生100年時代といわれる。しかしあるアンケートでは、100歳まで生きたいと答えた日本人は3割に満たなかった。アメリカや中国はその倍以上の方が100歳まで生きたいと思うと回答したそうだ。もちろん考え方や環境も違うので、一概にはいえないが、幸せという観点でただ長生きすればそれでよいということではなさそうだ。
人はいつか死ぬ。
この現実は変えられないことはわかった。じゃ次の質問をしたい。
「あなたはどんな最後を迎えたいですか?」もちろん死は老いや病気に限らない。
例えば、最近熊に関するニュースを毎日のように見聞きする。死者も多数でているが、私自身は熊がほぼいない四国に住んでいるので、どこか遠くの人ごとと思っている節があった。しかしもし自分が、あるいは身近な人がある日突然、熊に襲われて死んでしまった、と想像してみたら急に胸が張り裂けそうになった。考えたくもない。
歳を重ねて老衰で定命を全うする方もいれば、若くして死ぬ方もいる。災難にあって突然死ぬ方もいる。あってはならないが自死を選ぶ方もいる。
何歳まで生きるのか、どうやって死ぬのか。私たちはこれらを本質的には選ぶことができない。そのことを前提に、最後の質問をしたい。
「仮に、もし明日自分が死ぬとしたら、やり残したことはありますか?大切な人に伝えたいことはないですか?」
悲しみから希望へ
天理教では、人の死を「出直し」という。
一人ひとりの身体は親神様からの「かりもの」であり、いつかはその身体をお返しするときがくる。しかし、身体をお借りしている主体の「魂」は、滅びることはなく生き通しである。この命は今世だけ、一代限りではなく、また来世へ生まれかわってくる。
教祖は出直しのことを、「古い着物を脱いで、新しい着物と着かえるようなものやで」 と教えられた。
死は終着点ではないということだ。列車に例えると、終着駅であったとしても時間が経てば、新たな列車がやってくるのと似ている。行き止まりである近鉄天理駅だって、到着して人が降りたら、また新しい人が乗車していく。

加えて、出直すとすべてがゼロになり、リセットされるということではない。
その人生において「尽くした理」は親神様がちゃんと受け取ってくださる。つまり来世においても魂に理が持ち越されていく。また残された人々、教会にもちゃんとその理は残っていく。ここでいう理は「種、徳、いんねん」と言い換えるといいだろう。
そして尽した理とは、親神様に真心を尽くし教えをまもること。人のため、人をたすけるために心を尽くしたことである。[※1]
出直しは終わりであり、再出発でもある。途切れるわけでなく、未来へつながっている。
もちろんすぐ簡単に割り切れない境遇に立たされることもあるだろう。それでも必ず、そこには親神様の親心が込められている。
悲しみから希望への転換。
これが出直しに込められた本当の神意ではないだろうか。単に「死」を言い換えた言葉が「出直し」である、という短絡的なことではないのだ。
[※1]
人間は一代と思うから、身上事情あれば頼り無いと思う。 (中略) 短いと思てはならん。長いという、長い心持たにゃならん。長いという心の中に、身上自由なあと思う処、取り直し。末代という理は、これより無い程に。皆生まれ更わり/\と言う。よう聞き分け。この理分かれば、日々苦し中に楽しみあろ。 (中略) 運び損にならん程に、尽し損にならん程に。末代の理に受け取ってある程に。
おさしづ 明治34年9月27日

エンディングノートなんか書かなくていい
冒頭の一言、「相続のプロ」が言った真意、理想像はこうだ。
- いくらお金持ちだって、死ぬときに財産を来世へ持っていくことはできない。あらかじめ遺族に対し遺産の分配、整理を考えておいたらよい。
- 残された家族、親戚はみな仲睦まじく、揉めることなどはない。
- 普段から身近な人へ大切なことはしっかり伝えてきた。やり残したことはない。
お道の偉大なる先人先輩は出直しに際し、旅立つがごとく「あとはみんな頼んだよ」といって安心して出直していったと聞く。こういう死を迎えることができれば、どんなに良いだろうか。まさに終わりであり、再出発でもあると深く頷くところである。

先述の「何歳まで生きたいか?」、「どんな最後を迎えたいか?」という質問は、生きる喜びを感じることの大切さ、生かされている今日一日の価値を気づかせてくれる。そして、死と向き合うことは「どう生きるか?」という大きな問いにつながっていく。
まさに今、身体をお借りし、生かされている我々にできることはシンプルである。心一つが我がのものであり、その心通りに親神様がすべて良いようにお見せ下さる。その心を教えにあわせ、一日生涯と念じて、陽気心で精一杯歩むことだけだ。
最後に、先日の「終活・相続勉強会」でお配りした天理教版のエンディングノート(お道のつなぐノート)を紹介して締めくくりたい。
このノートをきっかけに、出直し(つまり死と生)に向き合い、そしてこの信仰をどう未来につないでいくのかを一度考えてみてはいかがだろうか?
立教188年11月1日
天理教繁藤大教会長
坂 本 輝 男
読んで良かったと思ったら「スキ」押してね♪
会長ブログにコメント機能を追加しました。ぜひご感想をお寄せください
天理教繁藤大教会の公式LINEに友達登録してもらうと神殿講話・過去動画の配信やブログなどを定期的に届けします♪
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)