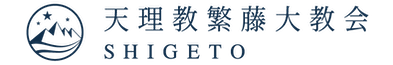(以下、本文)
立教189年、教祖140年祭を迎えるにあたり、思うところを述べて、全教の心を一つにしたい。
親神様は、旬刻限の到来とともに、教祖をやしろとして表にお現れになり、世界一れつをたすけるため、陽気ぐらしへのたすけ一条の道を創められた。
以来、教祖は、月日のやしろとして、親神様の思召をお説き下され、つとめを教えられるとともに、御自ら、ひながたの道をお示し下された。
そして、明治20年陰暦正月26日、子供の成人を急き込まれ、定命を縮めて現身をかくされたが、今も存命のまま元のやしきに留まり、世界たすけの先頭に立ってお働き下され、私たちをお導き下されている。
この教祖の親心にお応えすべく、よふぼく一人ひとりが教祖の道具衆としての自覚を高め、仕切って成人の歩みを進めることが、教祖年祭を勤める意義である。
おさしづに、
ひながたの道を通らねばひながた要らん。(中略)ひながたの道より道が無いで。
(おさしづ 明治22年11月7日)
補足・解説はこちら
と仰せられている。
教祖年祭への三年千日は、ひながたを目標に教えを実践し、たすけ一条の歩みを活発に推し進めるときである。
教祖はひながたの道を、まず貧に落ちきるところから始められ、どのような困難な道中も、親神様のお心のままに、心明るくお通り下された。
あるときは、
「水を飲めば水の味がする」
補足・解説はこちら
と、どんな中でも親神様の大いなる御守護に感謝して通ることを教えられ、また、あるときは、
「ふしから芽が出る」
補足・解説はこちら
と成ってくる姿はすべて人々を成人へとお導き下さる親神様のお計らいであると諭され、周囲の人々を励まされた。
さらには、
「人救けたら我が身救かる」
補足・解説はこちら
と、ひたすらたすけ一条に歩む中に、いつしか心は澄み、明るく陽気に救われていくとお教え下された。
ぢばを慕い親神様の思召に添いきる中に、必ず成程という日をお見せ頂ける。
この五十年にわたるひながたこそ、陽気ぐらしへと進むただ一条の道である。
今日、世の中には、他者への思いやりを欠いた自己主張や刹那的行動があふれ、人々は己が力を過信し、我が身思案に流れ、心の闇路をさまよっている。
親神様は、こうした人間の心得違いを知らせようと、身上や事情にしるしを見せられる。
頻発する自然災害や疫病の世界的流行も、すべては私たちに心の入れ替えを促される子供可愛い親心の現れであり、てびきである。
一れつ兄弟姉妹の自覚に基づき、人々が互いに立て合いたすけ合う、陽気ぐらしの生き方が今こそ求められている。
よふぼくは、進んで教会に足を運び、日頃からひのきしんに励み、家庭や職場など身近なところから、にをいがけを心掛けよう。
身上事情で悩む人々には、親身に寄り添い、おつとめで治まりを願い、病む者にはおさづけを取り次ぎ、真にたすかる道があることを伝えよう。
親神様は真実の心を受け取って、自由の御守護をお見せ下される。
教祖お一人から始まったこの道を、先人はひながたを心の頼りとして懸命に通り、私たちへとつないで下さった。
その信仰を受け継ぎ、親から子、子から孫へと引き継いでいく一歩一歩の積み重ねが、末代へと続く道となるのである。
この道にお引き寄せ頂く道の子道の子一同が、教祖の年祭を成人の節目として、世界たすけの歩みを一手一つに力強く推し進め、御存命でお働き下さる教祖にご安心頂き、お喜び頂きたい。
立教185年10月26日 真柱 中山善司
脚注一覧(天理教事典参照)
◆ 立教
一般に、宗教の歴史的始まりを意味する言葉として、「開教」などとともに使われている。
天理教では、親神の歴史的啓示にもとづいて、人間救済の親神の意志が表明され、それを実現する基礎が確定した時をもって立教としている。それは天保9年(1838)10月26日、大和国山辺郡庄屋敷村(現、天理市三島町)の中山家の主婦、みきが「神のやしろ」と定まった時である。
◆ 教祖年祭
教祖(おやさま)年祭は、天理教の教祖が、明治20年(1887)陰暦正月26日(陽暦2月18日)に、90歳で現身(うつしみ)をかくされて後、10年ごとに勤められている祭典。
◆ 親神様
親神・天理王命
天理教信仰においては、その信仰の対象となる神を「親神」と仰ぎ慕い、「天理王命」と唱えて、その守護を祈念している。
◆ 旬刻限
天理教立教の時、すなわち天保9年(1838)10月26日を表す語。時候や季節、特に物事の最も充実した時を表す「旬」と、特に限定した時を表す「刻限」との合成語である。
天理教は、教祖(おやさま・中山みき)が「月日のやしろ」と定まった時に始まる。この時は、「元初まりの話」によれば、人間創造の時、夫婦の「ひながた」となった「うを」と「み」に、「最初産み降ろす子数の年限(九億九万九千九百九十九)が経ったなら神として拝をさす」(『天理教教典』第3章参照)との親神の約束にもとづいた時である。つまり、この時は人間創造の時に予定されていたと言えよう。天理教では「旬刻限の理」として、立教の時間的限定面からの重要な契機とされている。
◆ 陽気ぐらし
陽気ぐらしとは陽気な心、すなわち明るく勇んだ心で日々を通ることである。親神はこの陽気ぐらしという言葉で、何よりもまず、人生の意義、人間の幸せが日々の暮らしの只中にあることを、しかも物や金や地位や名誉などといった自分以外の物事にあるのではなく、日々を暮らす自分自身の只中にあることを教えているのである。つまり、陽気ぐらしは人間の日々のあり方一つにかかっている
◆ たすけ一条の道
一般的に「たすけ」とは、他のものを助勢する意味であり、「一条」とは「ひとすじ」「ひたすら」と同義である。天理教では「たすけ一条」と熟語化して、「たすけたいとの心だけである」、「たすけのために専心すること」という意味で使われる。親神は、子供である人間をたすけることだけを考えている、すなわち「たすけ一条」の親心でおられる。このお道(天理教)を始めたのもこの親心からであり、お道は「たすけ一条の道」と言われる。したがって、人間も同じ心、たすけ一条の心になることが大切である。それは、人にたすかってもらいたいという心で日々を歩むことを意味している。この心は親神の思いにひたすら沿う行動であり、生き方である。
◆ 月日のやしろ
教祖(おやさま)の立場を表す言葉。「神のやしろ」とも言われる。「月日」は親神を示す言葉として使われており、「やしろ」は社で、一般的に神が鎮まる所を意味する。したがって、「月日のやしろ」とは、何よりもまず、親神の所在を表現したものと言える。
◆ つとめ
天理教で「つとめ」または「おつとめ」と呼ばれるものは、天理教の祭儀の中心となるものであって、特に恒例の祭典はつとめを勤めることが主要行事である。このつとめは、大きく二つに分けられる。一つは、親神がこの世に現れた目的の一つである「たすけ」(救済)を実現するために教えられたつとめである。これにもいくつか種類があるが、その中で最も根本的で重要なものは、「ぢば」において「かんろだい」を囲んで行われるつとめで、一般の教理書において「つとめ」といって説明してあるものは、このつとめである。これに対して、もう一つのつとめは、人間が親神に向かって、感謝したりお祈りしたりするために教えられたもので、「朝夕のつとめ」と呼ばれるものである。
◆ ひながた
一般的なひながた(雛形、雛型)の語義は、実物をかたどったもの、模型、原型ないしは様式、見本などである。教語として取り上げられるべき「ひながた」は、教祖(おやさま)が「月日のやしろ」としての立場で歩まれた50年間の生涯を、信仰生活の手本として仰ぎ、それを目標にして信仰生活を進めるべきであるという教理を含んだものである。「教祖のひながた」とか「教祖ひながたの道」などと言われる。これは信仰生活の具体的な目標を、教祖が通られた生涯の歩みの中に見つめ、それを手本として信仰の足どりを進めるように教えられたことによる。
◆ 成人
天理教の用語としては、「心の成人」というように、もっぱら精神的、人格的な成長、さらには宗教的な成熟という意味が強いが、原点においては、幼年者の成長することの意味で使われているところもある。ここでは前者の意味。
◆ 定命
原典の用語。人間の命(いのち)に定められている115歳の寿命のこと。「おふでさき」に次のように言われている。
ほこりさいすきやかはろた事ならば
あとハめづらしたすけするぞやしんぢつの心しだいのこのたすけ
やますしなずによハりなきよふこのたすけ百十五才ぢよみよと
おふでさき(第三号98-100)
さだめつけたい神の一ぢよ
ここに言われるように、定命まで生きるのに、「病まず・死なず(途中で死なず)・弱らず」に暮らすということが理想である。さらに、定命以上に生きることもでき、行く行くは、年をとらない、年寄りにならないと言われている。
◆ 現身
この世に姿をもって生きていることを言う。天理教では教祖(おやさま)について、「出直し」とは言わず、「うつしみをかくされた」または「御身(おんみ)をおかくしになった」と表現する。これは「教祖存命の理」にもとづいている。教祖は、明治20年(1887)陰暦正月26日、「二十五年寿命縮めて」(さ30・11・20)一れつ子供である人間の成人を急き込んで、御年90歳で、現身をかくされた。
◆ 元のやしき
「元のやしき」の略称で「おやしき」と呼ぶ。屋敷とは元なる「ぢば」のある中山家という屋敷のことである。もとより、ぢばは親神が人間・世界を創造した時の中心、すなわち、人間が宿し込まれた元の地点。したがって、世界中の人間にとっての生まれ故郷、親里(「おやさと」とも表記)である。
◆ よふぼく
漢字の「用木」に由来する用語と見られる。原典では「よふぼく」と表記し、慣用的には併用する。親神の世界救済、すなわち理想社会である「陽気ぐらし」の世界の建設を、建物の建築にたとえ、布教伝道にあたる者をそのために使用される用材としての「用木」に見立てた言い方であり、天理教布教伝道の場における人材を意味する。
◆ 道具衆
教祖の道具衆とは、親神の人間世界創造の目的である「陽気ぐらし」世界実現のため、救済活動に挺身する人を言う。「教祖の手足となって働く道具衆」というように使用され、よふぼく(ようぼく)と同義に考えられている。
◆ おさしづ
教祖および「存命の教祖の理」を受けて神意を取り次いだ「本席」飯降伊蔵を通して啓示された、口述の教えである。またその筆録を編集して成った書物を指し、天理教教義の源泉をなす三原典のうちの一つ。
◆ 三年千日
3年間の日限、すなわち約千日の日数を指す。信仰的実践にあたり、決意的に仕切った日限である。つまり、ある目標に向かって、この期間に信仰的努力を集中することにより、親神の創造的守護を願うことが一般化されている。特に、教祖(おやさま)の年祭を目指し、「三年千日」の期間を仕切って、年祭活動を展開することが多い。
◆ 成る理(成ってくる)
物事が成ってくるには、筋道があり、そのもとになるもの、また結果として成ってくることがある。「成る理」は、こうした筋道や、もとになるもの、成ってくることを指して使われる。
物事が成るのには、親神の働きと人間の心の両方がかかわっている。物事が成るのは、親神の働きによるのであるが、心次第と言われるように、誠の心に対して親神は働かれる。誠の心・精神が、物事が成るもと、つまり「成る理」である。
◆ ぢば
元初まりに、人間を宿し込まれた地点を「ぢば」といいます。すなわち、全人類の故郷であることから、ぢばを中心とする一帯を親里と呼びならわしています。ぢばには、親神様のお鎮まりくださる所として、天理王命(てんりおうのみこと)の神名が授けられ、ぢばを囲んで陽気ぐらしへの世の立て替えを祈念する「かぐらづとめ」が勤められます。人間宿し込みの元なるぢばに、その証拠として「かんろだい」が据えられ、礼拝の目標となっています。
◆ てびき
手引き、案内の意味である。親神は人間救済のために、いろいろな事象、特に身体の思いや事情のもつれなどを通して、現実のあり方に対する反省を促し、人生の正しい方向を指示して、救いの道へと導かれる。こうした身近な場面における救済のあり方からすれば、たとえば身を患い、困難な問題にあうことなどは、正しい生きかたを志向する契機ともなるし、救いの道に踏み出す土台ともなる。つまり、それは、親神のてびきの現れとして認識されるべきものとなる。
◆ 一れつ兄弟
人間はすべて親神を親とする同一兄弟姉妹であるという教え。人間は一人残らず同じ神の子として親神により創り出され、一人ひとりの身体を親神から借り、同じ親神の守護を受けて生きている。したがって人類はすべて、同一家族の一員であり、同じ親神の可愛い子供である。
◆ ひのきしん
天理教信者の積極的な神恩報謝の行為を、すべて「ひのきしん」という。漢字をあてれば、「日の寄進」であり、日々親神に寄進するという意味を持つ。ひのきしんは天理教信仰の行動化された姿そのものである。
◆ にをいがけ
「にをいがけ」とは、匂い掛け。お道の匂い、すなわち、親神様を信仰する者の喜び心の匂いを、人々に掛けていくことをいいます。真のたすかりの道にいざなうための働きかけです。親神様のありがたさを世の人々に伝え、信仰の喜びを広め分かち合うこと
補足・解説
◆ ひながたの道を通らねばひながた要らん
◆ 水を飲めば水の味がする
天保9年(1838年)10月26日、中山みき様(教祖)のお身体に親神様が入り込まれてからは、まず「貧に落ち切れ」との親神様の思召のままに、貧しい人々への施しに家財を傾け、貧のどん底への道を急がれました。かかる十数年の歳月のうちに、夫・善兵衞様のお出直しという大節に遭われましたが、かえってこの機に、「これから、世界のふしんに掛る」と仰せられて、母屋を売り払い、さらには、末娘のこかん様を浪速の地へ布教に赴かされました。このような常人には理解し難いお振る舞いは、親族の反対はもとより、知人、村人の離反、嘲笑を招かずにはいませんでした。その後さらに10年ほどのどん底の道中も、常に明るく勇んでお通りになり、時には食べるに事欠く中も「水を飲めば水の味がする」と子供たちを励ましながらお通りになりました。
◆ ふしから芽が出る
「おさしづ」の用語であり、また信仰の場において、しばしば用いられる教語でもある。身上(みじょう)のさわり(病・怪我など)や事情のもつれは「節」と教えられる。それは、病気に苦しみ、事情に悩む者に、真実の親なる神の存在を知らせ、わが身勝手な人間思案の心得違いを改めさせ、「陽気ぐらし」へ導こうとされる親神の子供可愛い親心の現れであり、人間にとってみれば、それは自己の心遣いを反省する契機、つまり「ふし(節)」を与えられていることになる。したがって、「ふしから芽が出る」と教えられるように、身上・事情という節を通して「ほこり」の心遣いを深く反省するとともに、そこに込められた親心を悟り、真実の心を定めて生きるところに親神の自由自在の守護が与えられる。
(天理教辞典より)
さあ/\ふし/\、ふし無くばならん。ふしから芽が出る。ふしより旬々揃えにゃならん。それより世界十分の理という。
おさしづ(明治22年5月12日)
◆ 人救けたら我身救かる
人にどうでもたすかっていただきたいと願い念じ、真実込めてにをいがけ、おたすけに努める中に、結果として、自らも結構なご守護を頂戴ちょうだいすることができるのです。
わかるよふむねのうちよりしやんせよ 人たすけたらわがみたすかる
おふでさき(第三号47)