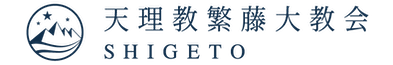読んで良かったら「スキ」押してね ♪
シリーズ 「かしもの・かりものの理」を深く掘る vol.2

先月の巻頭言で「早い信仰と遅い信仰」というタイトルで「かしもの・かりものの理」というお道の教えの土台について触れた。
神様、またその教えを信じるか否かではなく、それを厳然たる事実として「知るという境地」を目指していきたいという内容だ。未読の方は、まずはこちらのコラムをご一読いただきたい。
さて今回はその続編として、どのようにすれば上記の境地に近づくことができるのかについて、考えを深めてみたい。
シンプルで強い言葉はいらない
いつも私が文章を書いたり、お話をするときに意識していることがある。それはなるべくシンプルに短く、なにより分かりやすく表現するということだ。
なぜならば今の時代、あまりの情報過多ゆえに、そうでもしないと途中でスキップされてしまう。
例えばSNS上では、なるべく受けが良いように、短く強い言葉でまとめられたショート動画が流行り、映画やドラマは倍速で観るなど、「コスパ」や「タイパ」といった風潮が広がっている。
さらにAIの台頭も相まって、たとえ門外漢の分野であろうが、本を端から端で読まずとも、生成AIに要約してもらえば、ある程度は事が足りる。
実際かくいう私も、昔は図書館が好きだったのだが、ここ1〜2年はとんと足が遠のいている。

むろん、悪いことばかりではなく、知らず知らずのうちに誰しもその恩恵を受けているはずだ。そして、おそらくこの流れはさらに進み、社会はますます物事を単純化して理解しようとする傾向に向かうだろう。
今回の巻頭言もほぼ無意識のうちに、「かしもの・かりものの理を心に治めるポイントを3つにまとめて…」といった感じで、実際に書き進めようとしていた。
・
・
・
いや、本当にこれでいいのか。
とたんに、執筆が止まった。
この世界の真理を掘り下げていこうというのに、私がおこがましく単純化してしまってなるものか。
必要以上に「シンプルに、強く、分かりやすく」要約してしまうことで、反対に根っこのところから遠ざかってしまっている気すらしてきた。
自分は「分かっているつもり」になっているだけかもしれない。
一つ受け取り、ゆっくり噛みしめる
ここである話を紹介したい。
東本大教会の初代会長である中川よし先生の逸話である。
当時、上級教会の髙安大教会の役員に、佃巳之吉というおさとしで有名な先生がいた。その佃先生に話を伺いに行った時の話だ。
「先生一言で結構ですから、神様のお話を聞かせて下さいませ」とよしが言うと、佃は、
「よう見えた。それでは一つお話しさしてもらいましょう。あのな、およしさん、この道は朝起き、正直、働きというてなあ…」佃は話をはじめた。よしは、
「先生、ありがとうございました。もうこれで結構でございます。また、お願いします」と帰り支度を始め、立ちかけた。佃はおどろき、
「な、な、中川、は、は、話はこれからやが。ひ、人に話をさしかけて、どこへ行くのや」とあわてて引き止めた。よしは、畳に手をついて、
「先生、ただいまの一言のお話で、私のようなものには充分でございます。私は頭も悪うございますし、実行もにぶいものでございますから、たくさんお話を伺っても覚えていることができません。
ただいまのお言葉、朝起き、正直、働き、を三月なり半年なり実行さして頂いて、充分実行ができ、あとあとも続けられるということが分かりましたら、また教えを頂きに参ります」と答えた。欲と一言いわれれば、欲を去り、高慢と一言きけば、高慢をとる。それがよしであった。
一言の教理も、真に神の言葉と受け止め、押し戴いて、よしは、全身全霊をもって、これに応えたのである。
(引用)「大いなる慈母」 髙橋 定嗣 著
真理をわかったつもりで、おこがましくまとめようとしていた私の姿勢と真逆である。
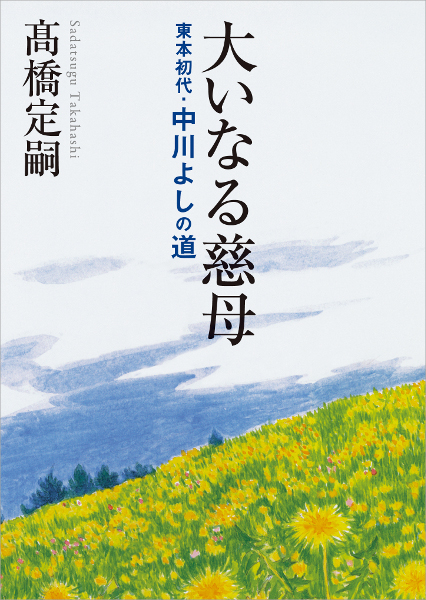

簡単に掴めたらわけがない
同じ文脈で、自分はできていないのに、毎回人に伝えていたことがある。
それは、修養科を終える方との面談のときである。いつも決まって、
「行く前と、行った後で何が変わりましたか?」という質問をする。その返答は人それぞれ異なる。ただ、それに対して私が返す言葉はいつも同じで、
「これから地元、つまり元の環境に戻るわけですが、その良い変化をできるだけ長く手放さないようにしていただきたい」という願いだ。
おぢばでの3ヶ月の修養期間を経て、本当に持って帰られるものはそんなに多くはない。神様から教えていただいたものを、本当の意味で自分の身に修めていくことは1〜2日で簡単にできることではないからだ。
私たちは「こうあるべきだ」「これさえやっておけば」という言葉に弱いものである。しかし、これだけ変化が激しく不確実な時代の中で、確かなものなんて一つもないと言ってもいいのではないか。

信仰という大きな問いに向き合う営みにおいて、必要なのは知識や技能を得る、積み重ねるといったプラスのベクトルだけではない。
立ち止まる、手放すといったマイナスのベクトルこそ大切になってくるだろう。凝り固まった「我」や、こうあるべきといった自分を無意識に縛り付けているある種の「呪い」は簡単にほどくことができないからだ。
真っさらに、先を永く。
前置きが長くなり本題に入る前に、私の反省文だけで紙幅が埋まってしまった。
だけど、これくらいでいいのかもしれない。
「かしもの・かりものの理」一つとっても、これまで数々の偉大な先人がこのテーマを深く掘り下げ、体現されてきた。
現時点で私がいくら思考をこねくり回しても、お道の先輩方の教話や書き物の二番煎じ、ただの焼き直しにすぎないことは明白である。
当初はこのテーマを1、2回のコラムで考えをまとめようとしていた。しかし繰り返しになるが、あえてできるだけスピードを遅らせてみようと思う。
具体的には、まさに今私が抱える疑問や葛藤、現代の世情や社会課題を織り交ぜながら、このテーマに向き合いたいと思う。
そして、中川よし先生のように、自分自身があらためて真っさらな気持ちで身に行い、身に修めていく中での気づきや変化にをもとに、悟りを綴りたい。はっきりいって自信はないが、実験的かつ挑戦的な試みである。
この続きを書くのがいつになるのか、またいつ完結するのかは現時点で全く予想できない。つまり赤裸々にいうと、それだけ私はまだまだ信仰的に未熟である。
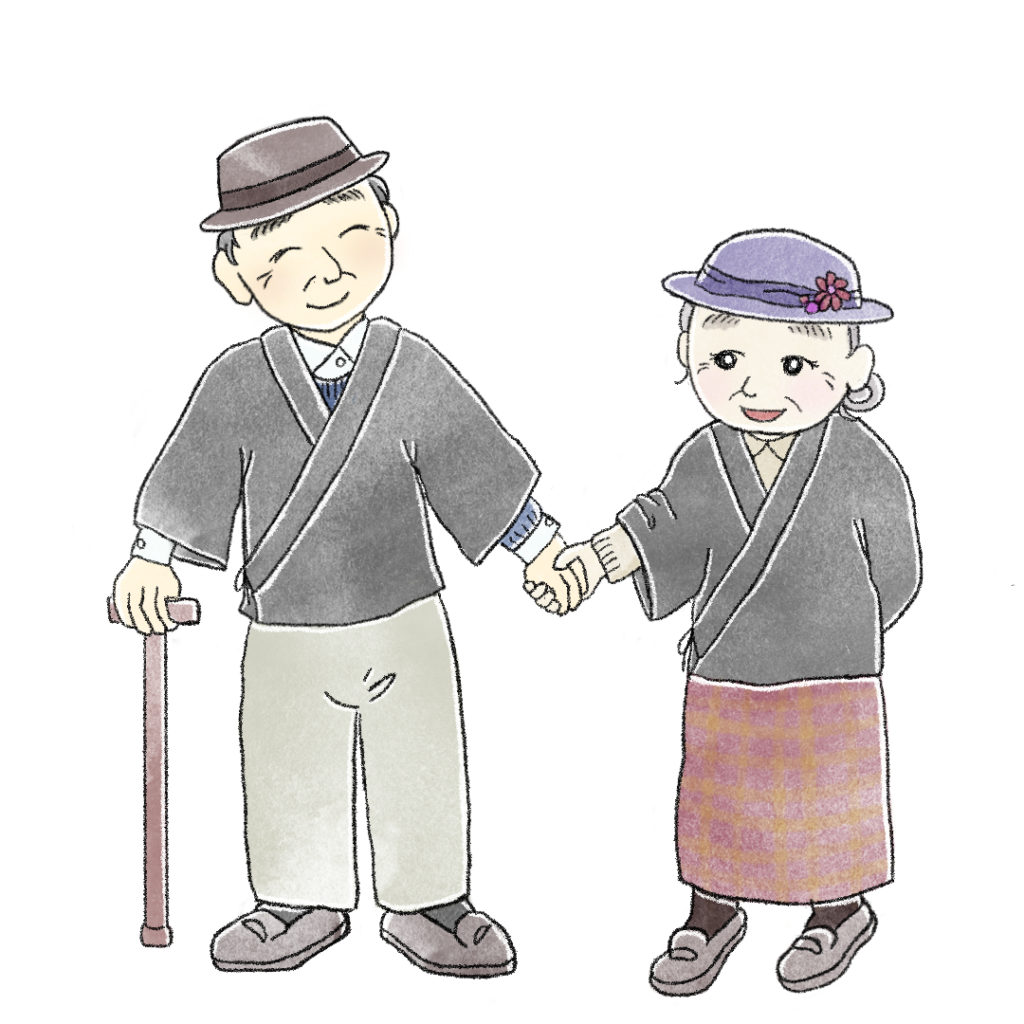
教祖のお言葉に、
「先を短こう思うたら、急がんならん。けれども、先を永く思えば、急ぐ事要らん。」
「早いが早いにならん。遅いが遅いにならん。」
133.先を永く(稿本 教祖伝逸話篇)
とあるように、皆様には遅々とした私の歩調に合わせてもらいつつ、できれば共に我が身に置き換えながら、先永くお付き合いいただきたい。
立教188年4月1日
天理教繁藤大教会長
坂 本 輝 男

読んで良かったと思ったら「スキ」押してね♪
会長ブログにコメント機能を追加しました。ぜひご感想をお寄せください
天理教繁藤大教会の公式LINEに友達登録してもらうと神殿講話・過去動画の配信やブログなどを定期的に届けします♪
-1024x1024.jpg)
-1024x1024.jpg)